毛沢東論―➁--終章-1宗教としてのマルクス主義、教祖としての毛沢東 覚え書 [ユーラシア・東]
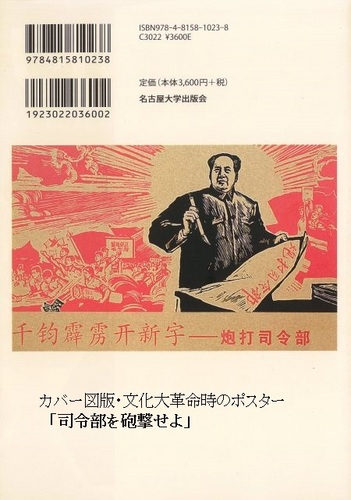
毛沢東論―真理は天から降ってくる
著者名 中兼 和津次 [ナカガネかつじ]
出版者 名古屋大学出版会
出版年 2021.4
終章-1宗教としてのマルクス主義、教祖としての毛沢東 覚え書
終章-1宗教としてのマルクス主義、教祖としての毛沢東 覚え書
ハンナ・アーレントは、ポルシェヴィズムを世俗的宗教として、また「真の信仰の代替物として、すなわち世俗化された社会から、生じた大きな現代的異教として」捉えた。「「世俗宗教」の出現自体が人間の宗教的欲求の不可避性の表現として、そして伝統的宗教に対する最高の政治的警告」つまり、マルクスか宗教を一種のイデオロギーとして見たのに着目し、両者の関係を逆転させ、イデオロギーを宗教として位置づけたのである。そうすればマルクス主義、そしてそこから派生したレ-ニン主義や毛沢東主義を、科学ではなく「宗教」だと捉えることができ、社会主義革命や建国後の運動あるいは歴史的事件をうまく説明できそう
である。
そこで、マルクスーレーニン主義とか毛沢東思想などといわず、思い切ってマルクス教やレーニン教ないしマルクス教レーニン派、または毛沢東教あるいはマルクス教毛沢東派と読み替えたらどうだろうか。そうすると、マルクスやレーニン、毛の言説や理論は「神」の言葉、いわば「聖書」となり、決して疑ってはならない、絶対的真理となる。もし神の言葉を疑ったり、「修正」したりしようものなら、レーニンがカウツキーを罵ったように、「背教者」というレッテルを貼られ、場合によっては政治裁判に掛けられ、処刑されかねない。かつてのソ連共産党員とは、マルクス教レーニン派という宗教団体、教団の信徒を指導、あるいは支配する神父や牧師、司祭に当たる。同様に中国共産党員たるものは、マルクス教毛沢東派なる教団の信徒たちにとってこの教団の神父や牧師、司祭に相当する。マルクス教レーニン派の大聖堂の神父にスターリンという独裁者がいたが、彼か提唱した社会主義下における階級闘争激化論という新しい教義に毛は強く彫響されていた。
この教団にはキリスト教と同様にさまざまな儀式かある。各地の教会にはレーニンやスターリン、あるいは毛沢東という教祖の肖像が飾られ、入信した信者たちは神父ないしは牧師(党書記)から「洗礼」の儀式を受ける。そのさい信者は「(神の国)共産主義実現のために奮闘努力します」と恭しく誓う。彼らの中で将来を嘱望された者は、「党校」なる神学校に行ってより深く教義を学び、教祖を通して神に絶対的な帰依を捧げる。
この教団の、一般の信徒は教祖を絶対疑わない。キリスト教徒が神を疑うだろうか?イスラム教徒はアラーを信じないだろうか?自分たちを救済してくれたのは教祖だと固く信じているか、信じ込まされている。毛沢東時代、真理は天から降つてきた。神、またはその代理である教祖たる毛沢東は、唯一の真理を語る絶対的存在であり、それを疑うのは「不敬」となる。仮に厳しい生活に追いやられても、時には飢餓の危機に見舞われても、信徒たちは教義や教祖を信じ続ける。時には地域の教会の悪辣な神父から搾取されたり虐待されたりしても、「悪いのは神父であって教祖様ではない」とか、「教祖様は神父の悪行をよく知らないのではないか」と言って、教祖に直訴したりする。彼らは心の中の神と教祖を慕い続ける。そして集会では「教祖様のご長寿をお祈り申し上げます【万寿無疆 まんじゅむきょう】」と祈りを捧げ、革命歌という『賛美歌』を歌ったりする。
大躍進とその後の空前絶後の大飢餓・飢餓が起れば、あるいは文化大革命で人々か殺し合い、すさまじい規模の犠牲者が発生すれば、普通の国では革命や大反乱が起き、政権は瓦解するはずである。・・・しかし、そうした劇的な変化か毛沢東時代の中国で起きなかったのはなぜだろうか?・・・餓死者数千万人を出しても中国は崩壊せず、共産党政権は微動だにせず、最高責任者毛沢東も失脚することはなかった。なぜだろうか?社会の隅々まで厳重な監視網が敷かれ、少しでも反党・反政府、あるいは反毛の動きを見せれば密告され摘発されてしまうからだろうか?それもあるかもしれない。しかし、大飢饉が起こり、社会か崩壊しそうなときには、密告網や警察網も崩れているのが普通である。・・・
いろいろ考えてみて、大躍進期に中国が崩壊しなかった要因として、最も可能性が高いのは次の二点ではなかろうか。第一に、そうした経済の混乱期に庶民は積極的に低抗するのではなく、消極的に、制度の裏をかくようなさまざまな行動、たとえばヤミ農地の開墾や食糧栽培とか、強制買付け食糧の隠匿とかいった、「反行為」を行い、それによって、多くの農民がある程度まで生存水準を維持できたことである。しかしこの要因は、餓死者が比較的少なかった地域における政権の相対的安定性を説明できても、飢餓が危機的状況にまで達していた地域について説明することは雖しい。村で半数以上の人が餓死し、人肉食(カニバリズム)さえ横行するといった悲惨な地域では「反行為」の手段さえ尽きてしまったはずである。
第二の、それ以上に強力な政権[安定化]要因とは、上述したある種の[宗教的]要因である。
四世紀の西欧でペスト(黒死病)が大流行し、人口が激減した時代かあった。・・・これが直ちに政治的激変をもたらしたという話は聞かない。多くの人々が病気になったために王権を倒す体力も気力もなくなったためだろうか?・・より重要な原因は中世キリスト教による精神的支配の強さだったように思われる。多くの民は死にゆく家族や仲間を見守りながら、必死になって祈りを捧げた。当時ヨーロッパの庶民にとって、キリスト教、口ーマ法王、そして教会(司祭)は絶対的存在だった。人々を支配し政権を担う王、ないしは領主は、こうした宗教的権威に従い、かつ教会を庇護していたわけであるから、王や領主に歯向かうことは教会に、ひいてはローマ法王に抗うことになったはずである。
これを毛沢東時代の中国に移し替えてみたらこうなるだろう。つまり、大躍進期開始後のあの大危機において、毛沢東教徒たちは教祖の毛主席を信じ、あるいはもう少し正確にいえば、毛があの大惨事の責任者だとは信じず、考えようともせず、悪いのは「地元の教会」の司祭や神父・牧師に当たる人民公社や県の幹部連中だと見なし、ひたすら消極的抵抗に走っていったのであろう。文革前の17年間、教科書、メディア、会議などあらゆる形式でみなか毎日繰り返し繰り返し公式イデオロギーを・・・(中略)・・植えつけられ・・・イデオロギーは社会全体の集団意識となった。ハンナ・アーレントが言ったようにイデオロギーが強固な宗教的教義になったといえる。
文革が始まる前に・・続ける
2021-10-30 11:00
nice!(0)
コメント(0)





コメント 0